このブログを読んでくださっているのは、男性のほうが多いでしょうか?
ちょっとした「女性の日常実感」ですが、こんなことがありました。
「おしゃれ」といえない、私なんかでも、この年になってくると、昔から持っているジュエリーなどが、相当増えています。若いときに、母や祖母からもらったものの、問題は、ずばりデザイン。ジュエリーにも、当然、流行があるんですよね。
【 初めての方へ 】
こんにちは、中山道子です。
私は、2002年以来、アメリカに投資をしてきました。
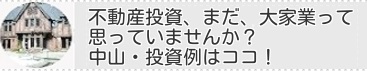
現在、米国では、随所で、景気回復の指標が出ていますが、格差問題には、歯止めがかかりません。今後のパフォーマンスは、いかに、地雷を避けて、安全堅実な投資機会を見つけられるかにかかってきます。海外投資にご関心がある方は、不動産や金融のプロの購読者をも多数抱える私の無料のメルマガに登録され、アメリカ不動産投資についての情報収集の一助とされてください。また、最新の体系的情報を一挙に手っ取り早くご理解されたい方は、2014年セミナーダウンロードをご利用ください。
【 最新記事 】
このブログを読んでくださっているのは、男性のほうが多いでしょうか?
ちょっとした「女性の日常実感」ですが、こんなことがありました。
「おしゃれ」といえない、私なんかでも、この年になってくると、昔から持っているジュエリーなどが、相当増えています。若いときに、母や祖母からもらったものの、問題は、ずばりデザイン。ジュエリーにも、当然、流行があるんですよね。
このブログをごらんのかたには、いろいろな方がおいでです。アメリカの物件をもっている方が、調べ物をしていることも多いようで、光栄に感じています。
このまえ、「ワシントン州のシアトルにいたとき買った土地を売却しなければいけないのですが、レアルターさんをご存知でしょうか?」というお問い合わせがありました。
file an extension (納税の)延長を申請する
そろそろ、年度末も終わり、申告の時期となってきました。アメリカでは、申告のことはtax return。納税申告することをfile a tax returnといいます。
2008年投資指南塾への多数のお申し込みありがとうございました。先週、初回を無事終え、みなさんに暖かく迎えていただき感激しました。
今回、本当を言うと、「ニッチなエリアだし、DVD作成をすれば、通しで見ていただけるかもしれないけれど、わざわざ、5回も、来てくださる方は、そんなに多くはないのでは?」と思い、会場は、当初、10人台でアットホームに催行するつもりのこじんまりした場所。
2012年追記:米国で言うレターサイズではなく、リーガルサイズです。ご質問があったので、ご確認まで。
2009年追記:しばらく前に、お客様に教えていただきましたが、オフィスデポでは、取り扱いがあるようです。前からかはよくわかりませんが、確かに、最近は、ネットサーチで出てきます。仕事で使う方以外は、私同様、B4カットがお勧めです、、、><
********
これも、りっぱな、日本からアメリカに投資するためのテクニックのひとつです?
アメリカに住まれたことがない方は、リーガルサイズというサイズの紙が存在することも、あるいは、ご存じないかもしれません。
本日2008年2月23日は、指南塾初回ということで、緊張しつつ、待ちに待った一日でした。地方からおいでくださった一部の方々は、私が1時過ぎに到着すると、すでに、お入りになっておいでで、頭が下がりました。皆さん、ご多忙でおいでなのに、、、
写真は、うわさの213ページの資料集。お遠い方は、もって帰るのも、ひょっとして、迷惑?とはいえ、永久保存版です!
英語で一般にcurbというと、歩道の縁石のような部分のことを言います。しかし、そのようなテクニカルな特定的な用語ではなく、不動産関係者がもっとルースに使う言葉が、curb appealという言葉。
今日は、投資プロパーというより、一般的な話です。
アメリカから、契約書が送られてくるのは、通常フェデックス。国際的な「宅配」ですね。
これに、公証が必要な文書は公証を行い、自分がサインするだけでよいものはサインを行い、また、返送します。
お客様や生徒さんが、アメリカ投資をはじめられるとなると、最初にお願いするのは、銀行口座の開設です。
このまえ、私のセミナーに、アメリカの不動産関係のプロフェッショナルスクールに、留学中の方がおいででした。お話をしてみると、ソーシャルセキュリティー番号(SSN, social security number)を未だ取得されていないということ。早速、調べてみて、対象となるようであれば、申請されるように、お薦めしておきました。
私のお客さんが、こんな記事のリンクを送ってくださいました。前向きのニュースですね、というコメントとともに、、、。わたしはまったく気が付いておりませんでした。S様にお礼を申し上げ、ご紹介をしたいと思います。
グリーンカードといえば、いわずとしれた、アメリカの永住権。
また、就業ビザなどを持っている場合は、ビザホルダー(visa holder、ビザ保有者)などといいますね。
家賃の入金が定期的にあればそれに越したことはありませんが、アメリカの典型的な契約を例に、入居者がちゃんといても、必ずしも、毎月振込みがしてもらえない、そういう場合を考えて見ましょう。
時々、野心家の方から、メールをいただきます。大体、若い男性が多いですね。「自己資金ゼロに限りなく投資したいです」といった感じの、、、。結果から言うと、それも、別に不可能ではありませんが、そういう場合、いろいろな「条件」がついてしまうことが多いです。
ある方に、大家さん業がなんたるか、ということをご説明していて、初めての方には、こういう図式が、わかりやすいかなと思うことがありました。
大家さん業対サラリーマンという対置は、自営業・ビジネスオーナー対サラリーマン、という対置だということです。
公証人とは、notary。Notary publicともいいます。その役割ですが、それは、
あなたが、サインする書類に
■ あなたがまさに、サインする人間本人であり
■ 強制されたりしていない
といったことを、対外的に、確認するために、利用します。
私にとっては、うれしい打ち合わせがありました。
Hさんは、30代の独身女性。お仕事、ずっと、がんばってきました。ただ、長く、営業をやってきたけれど、ちょっと、それが、苦しく感じる時期が来ていて、「今は、派遣です。はじめたばかりですが、いやなプレッシャーもなく、余計な気を使わなくてすむので、とても、気に入っています」ということでした。
ただ、どうしても、お仕事的には、月収から、貯蓄する余裕はないということです。そこで、将来の年金対策の一環として、これまでの貯蓄の一部を、アメリカ不動産投資にまわしてみたい、というお話でした。
不動産用語、というわけではないですが、ちょっと、英語流の言い方なので、取り上げてみます。それは、forced savings。意味は、強制的な貯蓄を(通常は継続的に)行っていくこと、です。
日本では、不動産は資産性があるといえば言えますが、長期にわたって値上がりしていくというイメージを持っているとしたら、それは、市場を知らない人でしょう。
日本では、物件は、
■ 上物は、15年から30年で、完全償却し、無価値に
■ 物件価値はあくまでそのときの土地の時価になるのが当然。
長期にわたって保有した物件につき、資金繰りを考えるときの、融資のキーワードは、アメリカのように「リファイナンス」ではなく、「建て替え」です。相対すれば、日本では、不動産の資産性は低く、アメリカやニュージーランドのような国は、高いのです。
時々、「1、2軒、購入したが、その先が分からない」という問い合わせをもらいます。私自身の経験に照らし合わせてみると、ある程度、自信を持って、何をやっているかが分かってくるためには、最低でも、4、5軒、やってみないとだめなんじゃないのかな、と思います。
コーチングをするようになったり、自分の歴史を冷静に振り返る余裕が出てきて、「投資家にとって必要な資質ってなんだろう」と考える機会がありました。
日本にいながらアメリカ投資をするとき、狂うのが、アメリカの休日。しかも、州の休日なんかだと、やはり、どうしても、わからなくなります。
もうひとつ、2008年2月6日今日困ったことが、、、
不動産投資には、コストやロスが付き物。これは、投資全般そうだろうと思います。
「自分は、ロスなく、資金を蓄積してきた」なんていう人がいたら、逆に、信じないほうが、正解です。
私自身、物件情報をご案内することをしておりますが、それについて、一言、申し述べさせていただきたいと思います。以下に、3つ、自分が思っていることを、書いてみました。
昨日2008年2月2日、大阪心斎橋セミナー行ってきました!皆様、ありがとうございました。
東京で前やった45分のセミナーを膨らませたもので、休憩を挟んで、2時間、お話をさせていただきました。
中山道子に連絡する
※念のため、 「 よくある質問 」 も、ご覧ください。
※複雑なご相談の場合は、お電話番号をご併記ください。
※ときどき、メールアドレスの入力間違いが見受けられます。
※2-3日しても返信がない場合は、お手数ですが再度お問い合わせ願います。
※ご相談の内容によっては、 「 お返事できないこと 」 もございます。ご理解ください。
※ご相談に対するお返事や、論評を、匿名の実例ケースとしてブログで取り上げる場合がございます。
メール送信先: 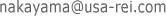
当サイトへのリンクについて
当サイトは、リンクフリーです。サイト内の各ページに、自由にリンクして頂けます。
ただし、著作権は、すべて「中山道子」に帰属します。
よって、引用される場合には、「リンクの掲載」が必須条件となります。